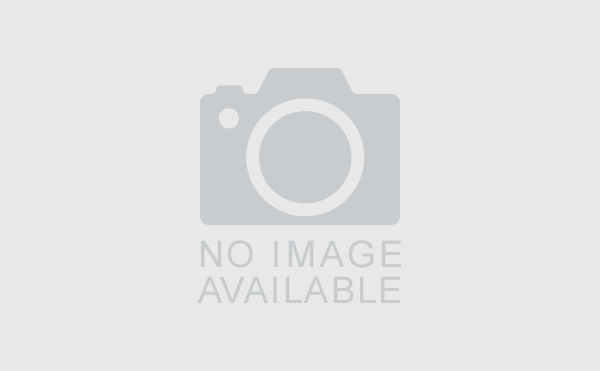ブローカ失語とは?言葉が出にくい理由と、家族が知っておきたい関わり方
「言いたいことは分かっているのに、言葉が出てこない」
「一生懸命話そうとしているのに、途中で止まってしまう」
このような状態がみられる場合、
ブローカ失語(運動性失語) と呼ばれるタイプの失語症の可能性があります。
この記事では、
ブローカ失語の特徴・原因・家族の関わり方のポイント を、
言語聴覚士の立場から分かりやすく解説します。
ブローカ失語とは?
ブローカ失語とは、
言葉を「考えること」はできているのに、うまく「話す形」にできない失語症 です。
主に、脳の左前頭葉(ブローカ野) が損傷されることで起こります。
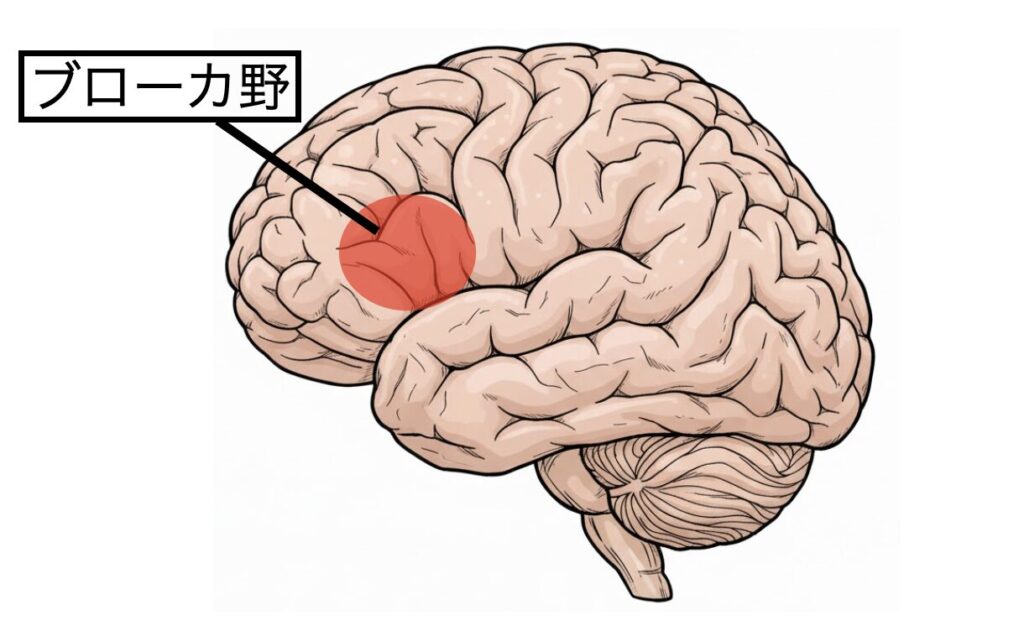
ブローカ失語の主な特徴
ブローカ失語では、次のような特徴がみられます。
■ 言葉がなかなか出てこない
- 話し始めるまでに時間がかかる
- 一語ずつ、区切るように話す
- 「……えっと……」と詰まることが多い
■ 文が短くなりやすい
- 「ごはん」「行く」など、単語中心
- 助詞(を・に・が など)が抜けやすい
■ 理解力は比較的保たれている
- 相手の話は分かっていることが多い
- そのため、「分かっているのに言えない」つらさ が強くなりやすい
家族から見ると、こんなふうに感じることがあります
ブローカ失語の方を支えるご家族から、よく聞かれる声です。
- 「時間がかかるので、つい先に言ってしまう」
- 「本人がイライラしてしまう」
- 「黙ってしまうことが増えた」
- 「話しかけるのが怖くなった」
これらは ご家族が悪いわけではありません。
ブローカ失語の特性上、誰にでも起こりやすい反応です。
ブローカ失語の方が感じやすい“つらさ”
ブローカ失語では、
- 自分が分かっていること
- 伝えたい内容
が 頭の中にある分、もどかしさが非常に強い という特徴があります。
そのため、
- 失敗を恐れて話さなくなる
- 間違いを指摘されると落ち込みやすい
といった心理的な影響も出やすくなります。
家族ができる関わり方のポイント(とても大切)
① 「待つ」ことが、いちばんの支援になる
言葉が出るまで、
少しだけ待つ時間 をつくってあげてください。
5秒待つだけでも、
本人が言葉を出せる可能性は大きく変わります。
② すぐに答えを言わない
「◯◯でしょ?」
と先回りして言ってしまうと、
- 話そうとする力
- 出そうとする意欲
が育ちにくくなってしまいます。
出なかったときだけ、
「最初の音」などの小さなヒントにとどめましょう。
③ 正しく言わせるより「伝わった」を大切に
多少言い間違えても、
「うん、伝わったよ」
この一言があるだけで、
話すことへの安心感 が大きく変わります。
ブローカ失語のリハビリと回復について
ブローカ失語の回復は、
- 少しずつ
- 波がありながら
- 時間をかけて
進んでいくことが多いです。
調子の良い日と、うまくいかない日が交互に来るのは
決して珍しいことではありません。
退院後に大切なのは「家庭での関わり」
病院でのリハビリが減ってくると、
- 話す機会が減る
- 間違えるのが怖くなる
といった状況になりがちです。
だからこそ、
家庭での安心できるやり取り が、回復を支える大切な土台になります。
まとめ|ブローカ失語の方は「分かっている」ことが多い
- ブローカ失語は「話すこと」が特に難しくなる失語症
- 理解は比較的保たれていることが多い
- 家族の「待つ姿勢」が、話す力を支える
- 正しさより「伝わった体験」を大切にする
ご家庭での関わりに不安がある方へ
家庭で使える失語症向けリハビリ教材 もご用意しています。ぜひ、ご活用ください。