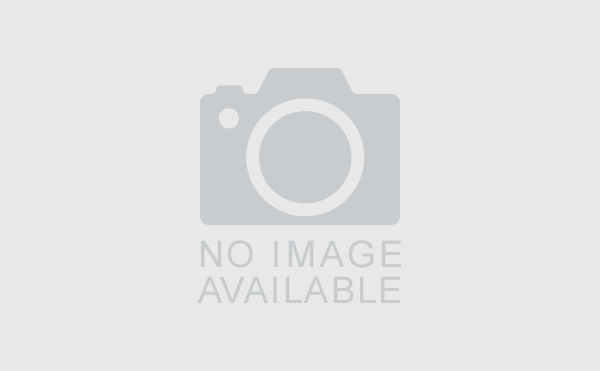失語症の家族ができる10のサポート
失語症は、脳の損傷によって「話す」「聞く」「読む」「書く」といった言葉の機能に障害が起きる状態です。言葉でのコミュニケーションが難しくなっても、それは知的な能力の低下ではありません。
大切な家族が失語症になったとき、「どう接したらいいの?」「何をサポートすればいい?」と戸惑うのは当然です。しかし、ご家族の温かいサポートこそが、リハビリの大きな力になります。
ここでは、失語症の当事者を支えるご家族ができる、実践的な10のコミュニケーションと生活のサポートをご紹介します。
🗣️ コミュニケーションの「聞き方」サポート(5選)
失語症の方との会話は、焦らず、当事者のペースに合わせることが大切です。
1. 「話し方」は、ゆっくり、短く、一文で
一度にたくさんの情報を詰め込まず、伝えたいことを簡潔な一文で区切って話します。難しい言葉や抽象的な表現は避けましょう。
(例)「朝ごはん何食べたい?」→「パン?ごはん?」
2. ジェスチャーや表情を最大限に活用する
言葉だけでなく、身振り手振りや大げさなくらいの表情を使って意味を伝えます。これは、相手があなたの意図を理解する大きなヒントになります。
3. 「はい/いいえ」で答えられる質問にする
質問をする際は、自由に文章を話させるよりも、うなずきや指差しで済む二択または「はい/いいえ」で答えられる形を選びます。
(例)「どこに行きたい?」→「病院?買い物?」
4. 相手が話すのを、最後まで待つ
言葉を探しているとき、途中で遮ったり、答えを急いだりするのはNGです。沈黙を恐れず、じっと待つ姿勢が安心感につながります。言葉が出てこなくても、「伝えようとしている」努力を認めましょう。
5. 理解しているか、こまめに確認する
「ここまで理解できたよ」「これは〇〇ということ?」と、話の要点を復唱したり、メモに書いたりして、お互いの理解がずれていないかを確認し合います。
✍️ 生活と心の「伝え方」サポート(5選)
言葉以外の手段を導入したり、生活環境を整えたりすることも重要なサポートです。
6. 筆談や描画をどんどん取り入れる
話し言葉に頼らず、メモ、ペン、ホワイトボード、またはタブレットを常に手の届くところに置き、筆談や簡単な絵、キーワードを書いて意思疎通を助けます。
7. コミュニケーションツールを作成する
銀行や病院など外出先で提示するための「私は失語症です」と書かれたカードやヘルプマークを作成・活用し、周囲の理解を求められるようにします。
8. 「完璧でなくていい」という姿勢を伝える
言葉の間違いや詰まりがあっても、「伝わったよ、大丈夫だよ」というメッセージを伝えます。完璧な発話を求めず、コミュニケーションが取れたこと自体を喜びましょう。
9. 言語聴覚士(ST)と連携し、家庭でできる練習を継続する
リハビリ専門職である言語聴覚士(ST)の指導を仰ぎ、家庭で取り組める発声や復唱の練習を、無理のない範囲で、生活の中に取り入れます。
10. 家族自身の時間と心のケアも大切にする
長期にわたる介護や支援は、ご家族にも大きな負担がかかります。休息を取る時間を確保し、地域の失語症友の会に参加して、悩みを共有したり、行政の支援制度を活用したりすることも大切です。