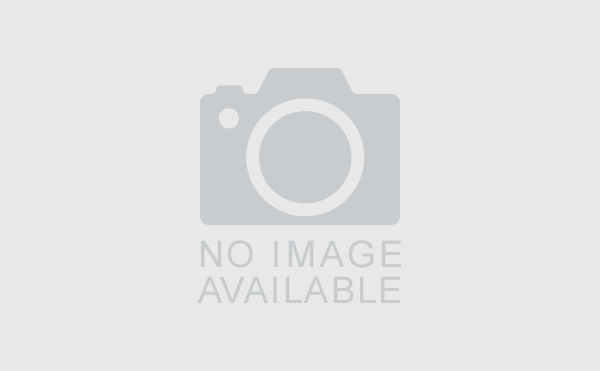ウェルニッケ失語とは?話しているのに伝わらない理由と、家族が知っておきたい関わり方
「よく話しているのに、内容がかみ合わない」
「こちらの話を分かっていないように見える」
「注意すると怒ってしまう」
このような様子がある場合、
ウェルニッケ失語(感覚性失語) と呼ばれるタイプの失語症の可能性があります。
この記事では、
ウェルニッケ失語の特徴・なぜ誤解されやすいのか・家族が困らないための関わり方 を、
言語聴覚士の視点から分かりやすく解説します。
ウェルニッケ失語とは?
ウェルニッケ失語とは、
言葉を「聞いて理解する力」が特に低下する失語症 です。
主に、脳の左側頭葉(ウェルニッケ野) が損傷されることで起こります。
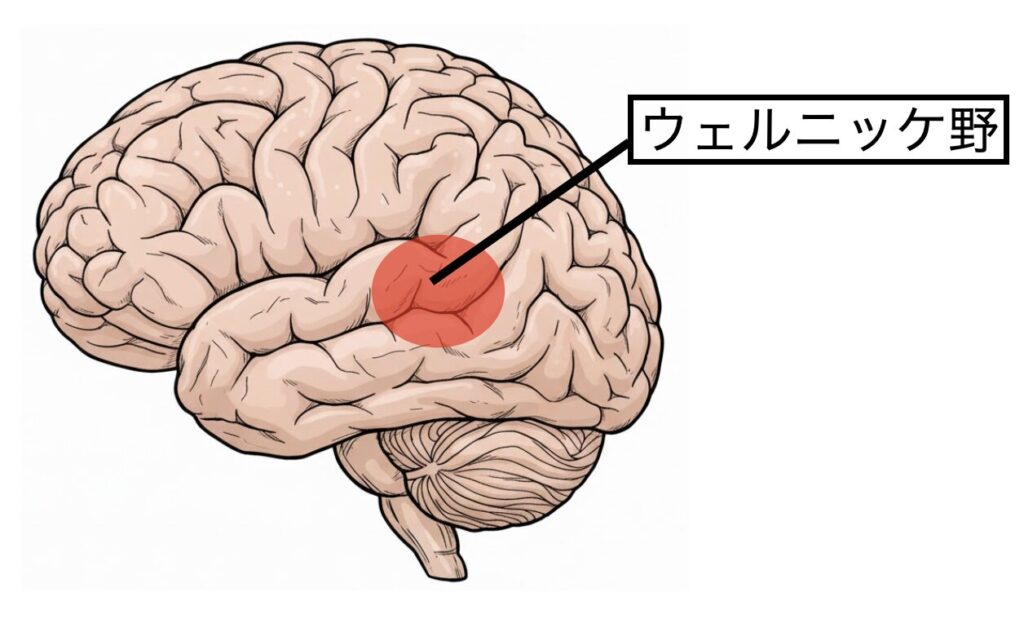
大きな特徴は、
- 話す量は多い
- しかし、内容がかみ合わない
という点です。
ウェルニッケ失語の主な特徴
■ 話し方は流暢に見える
- すらすら話す
- 話す勢いがある
- 文の形は整っているように聞こえる
そのため、
「言葉の障害があるように見えにくい」 ことが多いです。
■ 内容が伝わりにくい
- 言い間違いが多い
- 意味の合わない言葉が混ざる
- 質問と関係のない答えになる
本人は話しているつもりでも、
相手には意味が通じない ことがよくあります。
■ 人の話の理解が難しい
- 長い説明が分からない
- 早口だと理解できない
- 聞き間違いが多い
このため、
会話がすれ違いやすくなります。
家族が混乱しやすいポイント
ウェルニッケ失語では、
ご家族が次のように感じることがとても多いです。
- 「ちゃんと話しているのに、なぜ分からないの?」
- 「分かっていないのに、分かっているふりをする」
- 「注意すると怒る、否定される」
これは、
本人が“分かっていないことに気づきにくい”ため に起こります。
ウェルニッケ失語の方が感じやすい心理的な特徴
ウェルニッケ失語の方は、
- 周囲とのズレを指摘される
- 話が通じないことを責められる
ことで、
- 怒りっぽくなる
- 不安定になる
- 話すことをやめてしまう
といった反応が出ることがあります。
👉 これは 性格の変化ではありません。
家族ができる関わり方のポイント(とても重要)
① 話は「短く・具体的に」
長い説明は避け、
- 一文を短く
- 一度に一つ
を意識しましょう。
❌「あとでお茶飲んでから散歩に行こうか」
✅「今、お茶を飲みます」
② 「分かった?」と聞かない
「分かった?」と聞くと、
多くの方は 反射的に「分かった」と答えてしまいます。
代わりに、
- 実際に行動してもらう
- 指差しで確認する
など、行動で理解を確かめる 方が安全です。
③ 間違いを強く指摘しない
言い間違いをその都度訂正すると、
- 混乱が強くなる
- 感情的になりやすい
ことがあります。
まずは
「伝えたい気持ち」を受け止める ことを優先してください。
ウェルニッケ失語のリハビリと回復について
ウェルニッケ失語では、
- 「聞いて理解する力」
- 「意味を捉える力」
を中心に、少しずつ回復を目指していきます。
回復のスピードや程度には個人差があり、
時間がかかることも少なくありません。
退院後に起こりやすい困りごと
退院後、次のような場面で困りやすくなります。
- 説明を聞く場面(病院・役所など)
- 電話対応
- 来客との会話
こうした場面では、
家族が「通訳役」になること が助けになる場合もあります。
まとめ|ウェルニッケ失語は「分からないことに気づきにくい」
- ウェルニッケ失語は「理解」が特に難しくなる失語症
- 話し方は流暢でも、内容はかみ合わないことが多い
- 家族は「短く・具体的に」を意識する
- 指摘よりも、安心できるやり取りを優先する
ご家庭での関わりに不安がある方へ
家庭で使える失語症向けリハビリ教材 もご用意しています。ぜひ、ご活用ください。