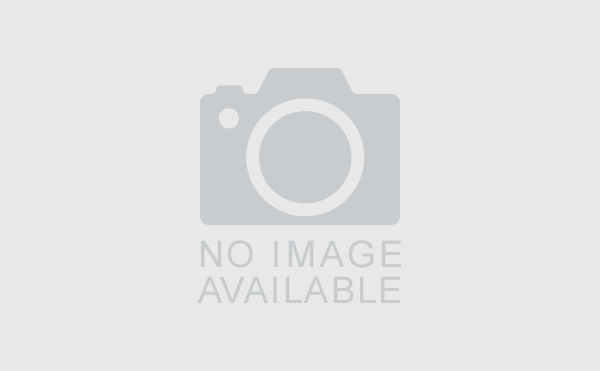失語症の分類
失語症の分類はどうして必要なの?
失語症の症状は人によってさまざまです。まったく話せない人もいれば、単語は出てくるけど文にならない人、話はできるけど相手の言葉が理解できない人もいます。これらの症状を整理するために、失語症はいくつかのタイプに分類されています。
この分類は、リハビリテーションの方針を立てたり、周囲の人がどのように接すれば良いかを知る上で非常に役立ちます。
失語症の主な3つのタイプ
失語症は、主に「言葉を理解する能力」と「言葉を話す能力」の組み合わせで、大きく3つのタイプに分けられます。細かく分ければもっと多いですが、まずは3つのタイプを理解しましょう。
1. ブローカ失語(運動性失語)
このタイプの失語症は、話す能力が特に障害されます。脳の「ブローカ野」という、言葉を発する命令を出す部分が損傷することで起こります。
- 症状:
- 言葉がなかなか出てこない、たどたどしい話し方になる。
- 「あ...い...す...きーむ」(アイスクリーム)のように、一つ一つの単語を苦労して発することが多い。
- 比較的、相手の言葉の理解は保たれている。
- 書くことも苦手になることが多い。
- 話したいことは頭の中にあるのに、口から出てこないという、もどかしさを感じやすいタイプです。
2. ウェルニッケ失語(感覚性失語)
このタイプの失語症は、言葉を理解する能力が主に障害されます。脳の「ウェルニッケ野」という、言葉を理解する部分が損傷することで起こります。
- 症状:
- 流暢に話すことができるが、内容がちぐはぐになったり、意味をなさない言葉(ジャーゴン)が多く含まれることがある。
- 「机」のことを「椅子」と言い間違えるなど、単語の選択を誤ることがある。
- 相手の言葉をうまく理解できないため、会話が成立しにくい。
- 話している本人は、自分の話がおかしいことに気づいていないこともあります。
3. 全失語
ブローカ失語とウェルニッケ失語の両方の症状が重度に現れるタイプです。
- 症状:
- 言葉を話すことも、理解することも、読むことも書くことも、非常に難しい状態。
- 発することができる言葉が、「はい」「いいえ」などごく限られたものになることが多い。
- 重度な失語症のため、コミュニケーションを取ることが特に困難になります。